ここは、心優しいひとたちのとまり木。


都会(まち)の喧騒を離れた裏通りに、その店はある。 バー「ピーチ・ハート」。気配り抜群でしっかり者の美形マスター趙雲氏と、ちょっぴり気の弱い天然癒し系のアルバイト姜維くんが切り盛りする、小さなカウンターバー。 今夜も、ちょっと疲れた男たちが羽根を安めにやってくる……。 PART.3 孔明さんの憂鬱 その日は、12月半ばとは思えないくらい暖かくて、穏やかな夜だった。 月曜日の7時過ぎ。 ピーチ・ハートのカウンターには、いつものように常連客の孔明さん。そして一番奥のテーブルでは、初めての二人連れの男性客が、黙ってビールを飲んでいる。 この時期、街にはイルミネーションやクリスマスソングがあふれていたが、ここはそんな世間の喧騒とは別世界だ。 静かな店内にはボサノバのメロディーが低く流れ、カウンターの上に飾られた小さなツリーだけが、季節を主張していた。 「ねえマスター、一度くらい付き合ってくれてもいいじゃない?」 カウンターに頬杖をついて、ブランデーのグラスを揺らしていた孔明さんが、出し抜けに言った。 今日は、まだそれほど酔っていないはずなのに……。 趙雲マスターを見つめる孔明さんの目がいつになく真剣で、ぼく(姜維)は柄にもなくドキドキしてしまった。 だけど、孔明さんの情熱的な視線を真正面から浴びながらも、趙雲さんは落ち着いたものだ。 「毎日こうやって、親しくお付き合いしてるじゃありませんか、差し向かいで」 (ひょえ〜〜。さすがだよな〜〜) こんなふうに、どんな場面もさらっとあしらえるようにならなきゃ、プロのバーテンダーとはいえないんだろう。 「だから、そうじゃなくて――」 孔明さんが、もう我慢できない、というふうに身を乗り出しかけたその時。 狙いすましたようにドアが開いて、もう一人の常連客 張飛さんが入ってきた。 「よっ。孔明ちゃん、またまたマスターを口説いてるね。そして、今日もあえなく撃沈?」 「ちょっと、張さん。せっかくいいところだったのに、じゃましないでよ」 孔明さんは、ほうっとため息をつくと、椅子に腰を落とした。 「やっぱりなあ。その様子じゃ、ずいぶん駄々をこねてたんだろ? さしずめ俺は、マスターの救世主ってわけだね」 大げさにピースマークを作って、孔明さんの隣に座った張飛さんに、ぼくは、あいまいな笑みを浮かべながらおしぼりを差し出した。 ほんの少し――。孔明さんが気の毒に思えたんだ。 「だいたい、お酒の弱い張さんが、どうして毎日ここへ通ってるわけ? まさかあなたもマスターを狙ってるんじゃないでしょうね」 思いもかけない突っ込みに、張飛さんは、口に含んだウイスキーのウーロン茶割りを噴き出しかけた。 「げふっ。ちょっ……冗談は、よしこさん〜〜♪」 それでも孔明さんはしつこく食い下がる。まるで、さっきの仕返しといわんばかりに。 「――もしかして姜維くん狙い?」 (おいおい……) 孔明さんのウインク攻撃に、今度は僕がずっこけそうになった。 「そんなわけないでしょ。俺はノーマルだよ、ノーマル」 「どうだか」 「マスター、この酔っ払い何とかしてくれよ」 さすがに辟易したのか、張飛さんはマスターに、助けを求めるかのように目配せした。 マスターは、そんな二人のやり取りを眺めながら、相変わらずニコニコしている。 「張飛さんは、私の高校の先輩なんですよ」 「あら、初耳よ、そんなこと」 大げさに驚く孔明さんに、張飛さんが得意げに言った。 「つまりさ、かわいい後輩の店がつぶれないようにだね、毎日サクラで来てあげてるのよ。ボランティアってやつだね」 「そうそう。ウーロン茶割り一杯でねばっていただいてますから」 「かーっ! いつもながらキツイね、マスターは」 張飛さんが趙雲マスターの先輩だというのは、ぼくも聞いたことがある。高校時代同じ山岳部で、生死をともにした仲だっていうのが張飛さんの自慢だった。ちょっと大げさすぎる気はするけどね。 「ま、ほんとのところは、一人でマンションにいてもつまんないからさ。ここだとエアコンもきいてるしね。腹減ったっていえば、何か食わしてくれるし」 「どうせそんなことだろうと思った」 もう一度グラスを揺らして、孔明さんはほうっと小さく息をついた。 そのとき、何気なく腕時計に目を落とした張飛さんが、孔明さんをつついた。 「孔明ちゃん、もうそろそろ時間じゃないの?」 「やだ、もうこんな時間? 大変、遅れたらママに叱られちゃう」 孔明さんの出勤時間は8時半。ここからお店までは20分かかる。時刻は8時を少しまわっていた。 孔明さんは少しあわてて荷物をまとめ、毛皮のコートを羽織った。 「どうやら今年も、マスターを落とすのは無理みたいね」 カウンターの上のツリーをそっと手に取ると、孔明さんは、独り言のようにつぶやいた。赤茶色に染めたロングのストレートヘアが、寂しげに揺れる。髪を掻き揚げるしぐさが妙に色っぽい。 「あーあ。今年のイブもひとりかあ。クリスマスもお正月も来なけりゃいいのに」 すねたようにうつむく孔明さんに、マスターが優しい笑顔を向けた。 「イブの夜もピーチ・ハートは営業してますよ。どうぞいらしてください」 「んー、もう、マスターのいじわる! こうなったら、イブの夜は私だけの貸し切りにしちゃおうかな。姜維くんも、その日は休んじゃっていいわよ」 「………」 突然矛先を向けられたぼくは、ただ笑っているしかなかった。 「それじゃ、マスター。イブの夜を楽しみにしてるわ〜〜」 孔明さんが出て行った後も、ぼくはしばらく茫然とその場に固まっていた。 (おいおい、どうしちゃったんだ、今日のぼくは。何でこんなに孔明さんが寂しげに見えるんだよ?) ――マスターも冷たいよな。 なんて、いつもなら思いつきもしない感情が頭の隅っこに引っ掛かっているのも、孔明さんの毒気にあてられたせいだろうか。 だけど、本当のところはどうなんだろう? 「ピーチ・ハート」でバイトするようになってから1年。マスターの周囲に、女性の存在を感じたことは一度もなかった。 まさか趙雲さんがゲイだとは思えないけど……。 やっぱり普通の男だったら、いくらオカマさんにモーションかけられても、その気にはなれないよなあ。 「すんません。そっちに移っていいですか?」 孔明さんが出ていってしばらくして、奥のテーブルに陣取っていた二人の客が、カウンターに移ってきた。 年は四十前後だろうか。二人ともどことなく胡散臭い。いわゆるちょっと違う世界の人、っていう匂いがするのだ。一人は見るからに強面のサングラス。もう一人は、無精ひげを伸ばした、ほんの少しだけ愛想のよさそうな男だった。 そんな二人を前にして、ぼくはかなり緊張したけれど、マスターの態度は普段とまったく変わらない。 「今の人、孔明っていう名前ですよね?」 無精ひげの男が、おもむろに尋ねてきた。 「え? ええ、そうですが、何か?」 「新宿のゲイ・バー『成都』に勤めてるとか。けっこう売れっ子らしいじゃないですか」 「………」 「ところで彼、どこに住んでるか知ってます?」 「――お客さま」 趙雲さんの声に心なしか緊張が走った。ぼくもカウンターの奥で、思わず耳をそばだてる。 「そういうことは、ご本人に直接お尋ねになったらいかがです? もし知っていたとしても、私は、自分の店のお客さまのことを他の方に話すような失礼なまねはいたしませんから」 「ああ、すまねえ。誤解させちまったようだな。実は、俺たちは興信所……っていうか、探偵なんだ」 サングラスをかけた方の客が、初めて口を開いた。外見通りの、凄みのある声だ。 「探偵さん……ですか?」 男が胸ポケットから取り出した名刺を受け取ったマスターの手元を、ぼくはしげしげとのぞき込んだ。 差し出された名刺には「夏侯探偵社 惇&淵 どんな難問も解決!」とあり、しかもごていねいに、にっこり笑った二人の男の似顔絵が添えられている。 (うへ〜〜、悪趣味) ふざけた名刺だ。ぼくもマスターも、なんとなく拍子抜けしてしまった。 「俺が惇、そっちが淵だ。調べてほしいことがあったら、いつでもどうぞ。何でも引き受けるぜ」 「依頼料も、ご相談に応じますよ」 淵と呼ばれた男が、無精ひげの伸びた口元に、満面の営業用愛想笑いを浮かべて付け加えた。 「――いえ、間に合ってます」と、マスター。 「お、俺も……」 張飛さんも、呆気にとられながら、こくこくと頷いた。 それから、二人の探偵が聞かしてくれた話は、ぼくたちを驚愕させるのに十分な、とんでもない内容だった。 「ある女性に、3年前に失踪したご主人を捜してほしいと依頼されまして」 無精ひげの男(淵)が切り出した話を、サングラスの男(惇)が引き取った。 「そのダンナによく似た人を『成都』で見かけた、っていう情報を手に入れたのはいいが、どうも決め手がなくてね。しかもオカマだってんで、見た目も全然違うしな。で、そのダンナがこの店によく通ってるって聞いて、押しかけてきたってわけさ」 「どうぞ、気を悪くなさらないでくださいよ」 無精ひげの愛想笑いとは裏腹に、ぼくたちはあっけにとられていた。 「そのいなくなったダンナっていうのが――孔明ちゃんだっていうのかい?」と、椅子から転げ落ちそうになる張飛さん。 「お、奥さんって(爆)!……孔明さんって、結婚してたんですかあっ?」 ぼくも、あまりの衝撃に、自分でも何を叫んだのか覚えていない。 あの孔明さんが……。女性と結婚していたなんて。 そんなことって。 ――これは、きっと悪夢だ。 「そりゃ俺も初耳だあ。何かの間違いじゃないの?」 張飛さんも、興奮冷めやらず、という顔で二人の探偵の顔を見つめた。 タイミングよくマスターが、その場のみんなに「これは私のおごりですから」と、よく冷えた生ビールをサービスしてくれた。そう、ぼくにも♪ そして、自分もぐっと一気にグラスを空けると、落ち着いた声で無精ひげの男に向かって言った。 「クラブ成都の売れっ子ダンサー、孔明さん。本名は確か諸葛亮さんだったと思います。ちがいますか、探偵さん?」 「お、その通りですよ。ってことは、やっぱり本物だな。惇兄、こいつは大当たりだぜ」 「確かに。間違いなさそうだ」 サングラスの男は、ビールを飲み干し、口元だけでにやりと笑った。 「で、どうするんです? さっそく奥さんに連絡して引き渡しますか?」 「いやあ、それがだなあ」 男は、何となくはっきりしない口調で言いよどむと、らしくない照れ笑いを浮かべた。 「奥さんは月英って名前なんだが、これがいい女でさあ。とりわけ美人ってんじゃねえが、年のわりにしっかりしてるし、何ていうかこう、こっちが恥ずかしくなるくらい気持ちがまっすぐで……」 「惇兄!」 「おっと、すまねえ、脱線しちまったな。いえね、月英さんは、自分のダンナがオカマだなんて、これっぽちも思っちゃいねえんだよ。なにか事情があって、姿を消したんだって信じてる。ただ、無事でいてくれればいい、それだけを確かめたい、っていうわけさ」 「それが、オカマバーで働いてて、こんなところでマスター口説いてるなんて……」 と、探偵の話に注釈をつけたのは張飛さんだった。 「ほんとのこと知ったら、ショックだわなあ」 ため息まじりに出した結論に、探偵たちも顔を見合わせてうなずく。 「だから、俺たちも悩んでるんだよ、どうしたもんかってね」 「いっそこのまま、見つからなかった、ってことにしておいた方が、奥さんのためかもな」 その時。 入り口のドアのところで、何かが落ちたような音がした。店の入り口の手前には衝立があって、カウンターからは直接、扉は見えないのだ。 マスターに目配せされて見に行ったぼくは、飛び上がらんばかりに驚いた。 「うわっ! 孔明さん! いつからそこにいたんですかっ? 衝立の陰で蒼白な顔をして立ちすくんでいるのは、孔明さん当人だった。 「ケータイを忘れたの。途中で気がついて取りに戻ったら、私の名前が聞こえてきたから、入るに入れなくて……」 ガタガタ震えている孔明さんの足元には、口の開いたバッグの中身が散乱している。さっきの音は、バッグが落ちた音だったのだ。 ぼくがそれらを拾い集めている間に、張飛さんが飛んできて、孔明さんを抱きかかえるえるようにして、カウンターに座らせた。 「俺たちの話、どの辺から聞いてたんだ?」 「月英は、ボクのことをオカマだなんて思っちゃいない……」 孔明さんは、こわばった手で、マスターが出した水の入ったグラスを口に運んだ。 「一番肝心なところは、ちゃんと聞いてたってわけだ」 突然、カウンターの下でケータイの着メロが鳴りだした。孔明さんが忘れていったケータイだ。遅刻してしまった孔明さんに、お店のママからだった。 「ごめんなさい。ちょっと急用ができちゃって。今日はお休みさせてください。ええ、明日は大丈夫です。きちんと行きますから」 できるだけ平静を装おうとしたんだろうけれど、声が震えている。 ようやく少し落ち着いてきたところで、そんな孔明さんを痛ましげに見つめていた張飛さんが、探偵たちに鋭い視線を投げた。 「なあ、探偵さん。もうこうなっちまったら、しょうがないだろ。きちんと孔明さんに話してやれよ」 「そうですねえ。こうなった以上、逃げも隠れもできませんからね」と、無精ひげは頭をかいた。 「調べている相手に見つかるなんざ、探偵としちゃサイテーだがな」と、苦虫を噛み潰したような顔のサングラス。 そうして、二人の探偵は、一部始終を孔明さんに話して聞かせた。 「月英は、今でもボクのことを待ってくれてるんですか」 「何かやむにやまれぬ事情があって姿を消したんだろうが、いつかきっと自分のところへ帰ってきてくれる。自分はあの人を信じている。だから、いつまでも待っています、とさ」 「月英――」 グラスを持つ手に涙が落ちた。 「ごめん……。ボクはこんなひどい男なのに。きみに愛される資格なんてないのに……」 打ちひしがれた蝶のように、カウンターに突っ伏す孔明さんの、あでやかなドレスの赤が、とても悲しい色に見える。 ぼくは、不思議な気持ちで、そんな孔明さんを眺めていた。 なぜって、姿かたちはどこから見ても女なのに、奥さんの名前を呼ぶ時の孔明さんは、まちがいなく男性の顔をしていたからだ。 「どうしてボクが結婚なんて、と思っているでしょう?」 孔明さんは、バッグから取り出したタバコに火をつけた。 「彼女は、月英はすばらしい女性です。彼女となら、こんなボクでもうまくやっていけるかもしれない、そう思っていたんです」 タバコの煙を長く吐きだしながら、月英さんとの過去を、ポツリポツリとつぶやくように語り始めた。 若い頃から同性に興味はあったが、自分がゲイだという自覚はなかったそうだ。それでも、女性に対してはまったく気持ちを動かされることがなく、いつしかそんな自分の将来に不安を抱くようになったという。 そんな時、大学で知り合った月英さんに、初めて異性として好意を持った。彼女はいわゆる「男前」な性格で、側にいても窮屈じゃない。それどころか、大きな懐に包まれているような安心感を覚えて、彼女となら結婚してもやっていけると思ったのだそうだ。 ところが、結婚してしばらくして、高校時代に憧れていた先輩に偶然出会った孔明さんは、誘われるままに彼と深い関係になってしまう。ずるずるとそんな生活を続けていたが、妻を裏切る心苦しさに耐え切れず、ついに家を飛び出してしまったというのだった。 「月英は、ボクがゲイであることも、彼女を裏切っていたことも知りません。もし、ボクの本当の姿を知ったら――」 孔明さんの手に、また涙が落ちた。 「わかった」 黙って孔明さんの話を聞いていたサングラスが、決心したように立ち上がった。 「ここにいる孔明っていう野郎は、俺たちの探してる諸葛亮とはまったくの別人だったってことだ」 「惇兄――」 「それでいいな? 淵」 「惇兄がそれでいいっていうんなら、俺は文句ねえよ」 無精ひげも、さばさばとした表情でうなずく。 ――そんなわけで、とサングラスの探偵はにこりともせず、マスターに言った。 「騒がせちまったな。どうやら、俺たちの早とちりだったようだ。無駄足踏んじまったが、おかげでうまい酒が飲めた。ありがとうよ」 「こちらこそ、いい話を聞かせていただきました」 「じゃあな」 それから、放心したように座っている孔明さんの肩にそっと手を置いて、その耳元に小声でささやいた。 「いつか必ず、奥さんのところへ帰ってやんなよ――」 サングラス越しに、優しい笑みが見えたような気がしたのは、ぼくの思い過ごしだったろうか。 探偵たちが出ていくと、店内は急にひっそりとした。 孔明さんは、あれきり黙ったまま。ぼくも張飛さんも、何と声をかけたらいいのかわからない。じっとりと湿った時間だけが過ぎていく。 「孔明さん」 趙雲さんが、孔明さんの前に1杯のカクテルを置いた。 「―――?」 「そんな顔は、孔明さんには似合いませんよ。さあ、これを飲んで、元気を出してください」 カクテルは、目にも鮮やかなマリンブルー。 「きれい……」 孔明さんは、うっとりとそのグラスを取り上げ、一口飲んだ。 「ああ、おいしい。胸のつかえが消えていく気分」 「マスター、それ、なんていうカクテル?」 知りたがり屋の張飛さんがたずねる。 「ブルー・マンデー。『憂鬱な月曜日』という名前のカクテルです」 「今日のあたしにぴったりすぎるお酒だわ」 孔明さんの顔に、寂しげな笑みが浮かんだ。 「いえ、本当はこのカクテルには、憂鬱な月曜日を吹き飛ばそう!っていう意味が込められているんですよ。そんなさわやかな味でしょう」 もう一口カクテルを飲んで、その余韻を楽しむように、孔明さんは目を閉じた。 「いつか……懐かしい場所に、帰れる日がくるといいですね」 「………」 「でもそれは、まだまだ先の話にしておきましょう。私も、常連のお客さまがひとり減るのは寂しいですから」 「マスターったら」 苦笑いする孔明さんの目蓋に、温かい涙があふれていく。 「あ、そうだ。さっきの話ですが、今度のクリスマス・イブ、孔明さんの貸切にしましょう。まあ、姜維くんと張飛さんは特別ゲストってことで。身内だけでささやかに過ごすイブもいいものですよ」 「ありがとう、マスター」 孔明さんは、手にしたおしぼりでそっと目じりをぬぐった。それから、 「わがままついでにもう一つお願いしてもいい?」 聞こえるか聞こえないかくらいの声で言った。 ――ボクの月英ちゃんにも、何かすてきなカクテルを作ってあげて。 |
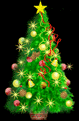 了 2005/12/20 |
|
|
【あとがき】 またまた7000ヒットを自爆!(笑)というわけで、ピーチ・ハートの第3弾をお届けします。 今回の主役(つーか、まな板の上のコイ)は、孔明さん。オカマってことで、思いっきり壊してしまったキャラですが、孔明ファンのみなさま、どうかお許しを。 何しろ、ふだんあまりにも真面目な丞相なので、こういう場所ではうんと遊んでしまいたくなるんですね〜。スミマセン。 作者としては、いつか孔明さんが、晴れて妻月英さんの待つ家に帰れる日がくることを願ってやまないのですが、その前に、趙雲マスターへの熱い想いを遂げることはできるんでしょうか。……やっぱ、それは無理か。ここって、ノーマルサイトだし(爆)。 今回、ゲストで登場の探偵さんたち。一応ビジュアルも作ってみたので、よかったらのぞいてみてください。決して二枚目じゃないけど(笑)、シチュエーションに応じていろんな顔を持っていそうで、私結構こういうキャラは好みです。 さて実は、これに続くクリスマス・イブのお話を考えていたのですが、本当に間に合うのか? 出来上がるのか? 胃の痛くなるような、スリルとサスペンスの日々になりそう、と思っていたら、本当に胃腸炎でダウンしてしまったというおマヌケな作者であります(笑)。 そんなわけで、後日談はまたの機会に。 【カクテル ブルー・マンデー】 ・ウォッカ 45ml ・コアントロー 15ml ・ブルー・キュラソー 1tsp(小さじ1杯)を、ミキシンググラスでステアしカクテルグラスへ。 マリンブルーが目にも鮮やかなこのカクテルは、美しい色あいには不似合いな「憂鬱な月曜日」という名前を持つ。'87年10月19日の月曜日、ニューヨーク株式が史上最大の暴落をしたいわゆるブラックマンデー。その日、ウォール街の片隅のバーで、このカクテルが生まれたという。「憂鬱な月曜日を吹き飛ばし、前向きに生きよう!」という願いを込めて。 |
|
|