| 今月の「お気に入り」は、ちょっといつもと雰囲気を変えて、「史記」の作者である司馬遷について取り上げてみたい。「史記」そのものを論じるにはまだまだ勉強不足だし、何よりも司馬遷という人の生き方そのものに、非常に心惹かれたからである。 私が高校時代に使っていた参考書に、藤堂明保先生の書かれた「基礎力漢文」という本があった。残念ながら今はもう手元には残っていないが、実にすばらしい内容で、漢文とその背景に広がる中国文化や歴史の面白さを私に教えてくれたのは、この一冊の参考書だったといっても過言ではない。 その中の「史記のこころ」という一節で、私は初めて、司馬遷の数奇な生涯と「史記」が書かれた経緯を知ったのだった。 それまでも、小説やマンガなどで、史記に描かれた世界に触れていたし、この時代に生きた人たちが大好きだった。けれど、司馬遷がどんな思いでこの書物を著し世に残したのか、その真意に気づいたとき、それまでとはまったく違う感動、身の震えるほどの衝撃に突き動かされたのである。 その感動をみなさんにもお伝えしたくて、つたない文章ではあるが、私の中の司馬遷への想いを語ってみたい。 それでは、「史記」の旅へ――。 中国には諸々の歴史書が存在するが、中でも最も日本人に親しまれ、愛されてきたのが、「史記」ではないだろうか(「三国志」は、歴史書である「正史」よりも、物語としての「演義」の方が有名だろう)。 私が実際に「史記」そのものに触れたのは、高校の漢文の授業が初めてだった。しかつめらしい教科書に、ぎっしり並んだ旧漢字……。しかも「史記」全体からすれば、ほんの一斑に過ぎないたった数ページの文章でさえ、私を感動させるには十分すぎるほどだった。 中国古代史のめくるめくようなおもしろさ、さらに歴史の悠久さと非情さ、その中で、ちっぽけでありながら、なお偉大な光輝を放ってやまぬ人間の営みのすばらしさ……を、初めて私に教えてくれた、それが司馬遷の「史記」だったのである。 司馬遷は、紀元前145年、山東省竜門に生まれた。父の司馬談は、「太史令」という暦、天文、歴史記録をつかさどる官吏だった。 太古の史官というものは、人間の歴史と地方万般の事象を心得た、いうならば天地世界のすべて、過去から未来までをも見つめうる聖職だったという。 古来、天に対して(いいかえれば、自己の良心に対して、ということだ)事実を報告する、という固い決意と責任を負うものであり、そのためにはときに権力と激しく争わなければならず、圧迫され、命を落とすことさえあったのである。 それほど崇高な太史令の伝統に、司馬談は絶対の誇りと強い使命感とを抱いていた。だが実際には、皇帝の権力が強大になるにつれ、「太史令」の職権は名目だけのものとなってゆく。 ときの皇帝 武帝は、皇帝専制の強力な独裁政治を確立しており、その絶対的権力のもとでは、史官はもはや一介の属官にすぎなくなってしまっていたのだ。 前110年、前漢の黄金時代を築いた武帝は、泰山において天地の神を祭り、漢帝国の完成を記念する壮大な封禅(ほうぜん)の式典をあげようとした。本来ならば、史官がその儀礼を計画し主催すべきであるのに、司馬談は式典について何の相談も受けなかったばかりか、それに参列することさえ許されなかったのである。 ああ――! いにしえの史官の誇りはいずこに失せたか。無言のうちに宇宙を統べている「ある実在」、神聖にして絶対なるもの―人々はそれを「天」と呼んだのであるが―に対する人々の慎ましさや敬虔さは、もはや消え去ってしまった。正義は死に、地上の権力のみが横行している……。 これを憂い、かれを憤り、悶々のうちに、ついに司馬談は病に倒れてしまう。おりから雲南へ遠征中であった息子の遷が、やっと洛陽に立ち戻ったとき、父は命旦夕にせまっていた。 病床の父は息子の手をとり、悲憤の涙を流しつつ切々たる言葉を残す。 「我が先祖は周室の太史である。汝もまた太史となって先祖に続け。泰山の封禅の盛典に列せられなかったのは、ああ、これも運命であろう。だが、余は太史令として歴史を記す立場にありながら、完成することができなかった。遷よ、余が死ねば、汝は必ず太史となり、余が論述せんとしたことを忘れてはならぬぞ。余の志を継ぎ、余が果たせなかった歴史記述の事業を成し遂げよ。汝、それ思えよや!」 絶叫ともいえる魂のほとばしりを残して、司馬談は帰らぬ人となった。 ときに、司馬遷36歳。3年の後、彼は父の後を継いで太史令に任じられたのであった。 それからは、父子二代の心血を注いで、ひたすら「史記」の執筆に精魂を傾ける日々が過ぎてゆく。 ところが、太史令となって8年、思わぬ不幸な事件が司馬遷を待ち受けていた。 前漢の七世皇帝武帝は、その名のとおり勇武の人だった。四方に遠征軍を派遣して漢の版図を広げ、北方異民族の雄匈奴に対しても、衛青や霍去病らの将軍を用いて正面から戦いを挑んでいた。 ときに李陵という気鋭の青年将校が、わずか五千の兵を率いて匈奴の領域深く進撃した。やがて漠北の荒野で、李陵軍は匈奴の大軍と死闘を展開する。いかに勇猛果敢な漢軍といえど、味方に十数倍する敵には抗しがたい。最後まで奮戦した李陵であったが、ついに捕らえられ、投降のやむなきに至ってしまった。 武帝は、この敗戦の報にいたく激怒した。おりしもその後、「李という将軍が匈奴に戦術の教練をしているらしい」という消息が聞こえると(これはもとより李陵のことではなく、以前から匈奴に帰化していた別の李姓の男のことであったのだが)、ついに李陵の一族を捕らえて皆殺しにしてしまったのである。 宮廷の人々は皆後難をおそれ、武帝に媚びへつらって李陵の罪科をあげつらい、彼の非を唱えた。が、そんな中にあって、ひとり敢然として李陵の功の大なるを説き、その弁護に立ったのが司馬遷だった。 晩年、友人にあてた手紙の中で、司馬遷は往時を述懐し、そのときの心境をつぎのように語っている。 「自分はかつて李陵と同門であったが、格別彼と親しかったわけではない。しかし、その人となりを見るに、彼は信義の人であり、常に我が身を顧みず、身をもって国家のために殉ぜんとする志を持っている。まさに、李陵には国士の風がある。臣下として、万死に一生を顧みずに主家の難に赴くことは、それだけでまれに見る貴いことではないか。今、ひとたび敗れたからとて、自分は宮廷にあって身を全うし、妻子を保っている諸臣が、皆われもわれもと李陵の非をあげつらうとは何たることか。自分は、まことに一人これを悲しむのである。さらに李陵は、その率いる歩卒はわずか五千に満たない。匈奴は国を挙げてこれを攻め囲んだ。千里を転戦し、矢は尽き道はきわまり、しかも救兵は至らず、士卒の死骸は積んで山をなすほどだった。しかるになお、李陵がひとたび呼んで軍士をいたわれば、皆身を起こして涙を流し、血をぬぐって再び空拳をふるったのである。思うに李陵は兵士と苦楽を共にし、よく部下に死力を尽くさせた。いにしえの名将といえども、これにまさらないであろう」 司馬遷の澄みきった目には真実が見えていたのだ。彼は、己の信ずるところに従い、事実のみを述べた。だが、彼の忠心からの正義の弁護は、正論であったにもかかわらず、かえって武帝の怒りに油を注ぐ結果になってしまった。 司馬遷は捕らえられて獄に下され、ついに宮刑(睾丸を切って不能者とする極刑)に処せられることになる。 宮刑は一名を腐刑ともいい、最も恥ずべき刑であった。この刑を受けた者は、生まれもつかぬ不具者となり、男であって男ではなくなるのだ。士大夫階級の者からは「かたわ者よ、日陰者よ」と後ろ指をさされ、人間扱いされなかったという。 故なき罪におとしめられ、死にもまさる恥辱を受けた司馬遷の悲しみと憤りはいかばかりだったか。 (死のう――) 何度、彼はそう思ったかしれない。しかし、そのたびに父の最期の言葉が耳の底によみがえり、今にも倒れそうな司馬遷の心を支えた。 ――余死すれば、汝必ず太史となれ。太史とならば、吾が論著せんと欲せし所を忘るるなかれ。汝、それ念(おも)えよや! 暗く冷たい石むろにつながれた司馬遷の胸に、ふつふつと熱い思いがたぎっていく。 (歴史を書かねばならない。死ぬことはできない。たとえ生き恥さらしても、生きて、歴史を書かねばならない……) 「父の志、我が信念、なんとしても貫かねばならぬ!」 権勢に対して敢然と筆をとった、いにしえよりの史官の不屈の魂が、牢獄の中に炎のごとく燃え上がったのであった。 やがて3年後に大赦にあって出獄した司馬遷は、前91年に55歳で没するまで、その余生を「史記」全百三十篇の執筆に傾け尽くした。 「史記」には、帝王の伝記である「本紀」や諸侯の伝記である「世家」とともに、まったく個人、それも名もない刺客や市井の侠客、稀世の悪人や酷吏と呼ばれた人たちにさえ光をあてた「列伝」が収められている。 七十篇にのぼるこの「列伝」の最初に、伯夷、叔斉の物語が置かれているのであるが、これはおそらく偶然ではあるまい。 かつて周の武王が、武力にまかせて悪逆な殷の紂王を討たんとしたとき、武王の馬のくつわを押さえて「暴をもって暴にかえる」行為を諌めたのが、伯夷、叔斉の兄弟だった。もとより二人の諫言は受け入れられるはずもなく、武王は殷を滅ぼし、天下は周の天下となった。 二人は暴力の横行する世に絶望し、周の粟(ぞく)は食わぬとて、首陽山に隠れて蕨(わらび)を採って食べていたが、ついに餓死して果てたという。 「天」は神聖にして絶対なるもの。 太古より人はこれを畏れ敬い、自己の鑑としてきた。天は何も言わぬけれど、常にはるかに人間界をみそなわしているのであり、その裁きは公平で、いつも善に味方するという。 ……だが、本当にそうだろうか? 伯夷、叔斉は明らかに善人であって、仁を積み、行いを清くしたにもかかわらず、かくのごとく餓死しなければならなかった。また、孔子の弟子の中で最も期待された顔淵だったのに、彼は貧乏でろくなものも食べられずに若死にしている。 かと思えば、悪逆非道の限りを尽くした盗賊が、何の罰も受けずに天寿を全うしている例がある。 天が善悪に報いるやり方とは、いったい何なのだ? 司馬遷は、ふと我が身を顧みずにはいられない。絶対者皇帝のもとでは、武帝の意に逆らうものは正と邪のけじめもなく獄に落とされ、忠誠のまことを尽くす人さえ、一朝にして国賊と見なされてしまう。それが今の世の中なのだ。 司馬遷が、生き恥さらしてまで書き綴ったものがここにある――。 彼は書かずにはいられなかたのだ。魂の底から噴き上げる怒り、絶望、悲嘆、慟哭。それらすべてを叩きつけるために。 「天道は是か、はた非か――」 彼は、全篇を通して問い続ける。それは「史記」の根底を流れるテーマであると同時に、司馬遷自身の過酷な運命に対する呪詛でもあったのだ。 もし天道が非であるとすれば、天すら信じられないとするならば、人は何を信じればよいのだろう? 司馬遷は、自分を信じた。自分の書いた歴史を信じた。これこそが、「史記」こそが、己の天道なのであると。 絶望のどん底にありながら、なおこれほどの自信と抱負を内に秘めて書かれた「史記」は、だからこそ現代もなお、圧倒的な迫力と感動で、読む者を惹きつけて離さない魅力を持っているのではないだろうか。 |
| 2006/2/1 |
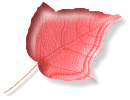 前述の藤堂明保先生の「史記のこころ」をずいぶん参考にさせていただきました。 なにしろ現物がもう手元にないもので、はっきりとは分からないのですが、 文中、引用させていただいた部分もかなりあると思います。ありがとうございました。 |
|
|